
|
<< 2026年1月 >>
記事カテゴリー
月間アーカイブ
|
記事カテゴリー:すべての記事
2016-02-11 09:57:37
新学期を前に新一年生のママたちの間では
学習机の話題が少なからず出てくるのでは無いでしょうか。 以前は入学とともに揃えることが慣習のようになっていた学習机ですが、 最近ではリビング学習の流れもあってか、購入のタイミングもそれぞれ異なるようですね。  ●学用品をまとめたいから入学時に 学習机で勉強するかどうか、というよりも学用品をまとめる場所として学習机を用意される方も。 1年生のうちは教科書も少ないですが、ランドセル、文具、週末に持ち帰る上履き、給食エプロン…などなど。 他にも通信講座のテキストや、習い事の道具も一箇所にまとめるために学習机があると便利だとか。 やはり学用品をまとめるうえで、学習机は機能的でしょうし、 一箇所にまとめてあると、お子さんも管理しやすそうですよね。 宿題をする場所としては 学習机を使うこともあれば、低学年のうちはリビング学習を選ばれる方もいらっしゃるようです。 ●帰りが遅くなり始める高学年になってから リビング学習を選ばれている方でも 「そろそろ一人で使える机が必要になるかしら」と考え始めるのが 帰りが遅くなってくる中高学年になる頃とか。 特に弟や妹がいらっしゃるご家庭の場合だと、 早くに食事を済ませたい下の子たちと、食事の時間になって帰宅し宿題をする上の子が同じタイミングでテーブルを囲むことになり、 お互いに気が散ってしまうことが理由のようです。 また、中高学年に限らず、 リビング学習だと、夕飯時にいったん宿題を移動させたり消しゴムカスを掃除したり…と面倒になることも。 やはり学習机がある方がお互いストレスが無い、と購入に踏み切るご家庭もあるようですね。 ●ランドセル置き場があれば机にこだわらない方も 机が無いとランドセルなどの学用品はどうしているの? と気になるところですが、 市販のランドセルラックや 造り付けの収納の一部をランドセルに充てたり、 これまではおもちゃが入っていた一角をランドセル置き場に変えたり、と いろんなやり方があるようです。 ランドセル置き場=学習机 とこだわらなければ、 選択肢は広がりますね。 「机を用意したけど結局、こたつ机で高校卒業まで勉強していた」とか。 「入学早々、自室の机で勉強する習慣が身についた」とか。 お子さんのタイプによっても机が必要になるかどうかは異なるのかもしれません。
2016-02-09 09:56:52
小さなお子さんがいらっしゃると飲み物をこぼすことも少なくないのでは?
いやいや、子どもに限らず、酔っ払いの大人だって手元があやしく飲み物をこぼす事も…。 「カーペットとか布にこぼしちゃうと洗濯が大変だから、何も敷かずにフローリングにしてるの」 なんて方もいらっしゃると思いますが、 フローリングでも油断ができない意外にやっかいなジュースをこぼした後始末。 いざという時のために知っておくとスマートに処理できますよ。  ●まずは乾いた布で拭き取りましょう ベタベタするからと、最初から濡れ雑巾やウェットティッシュで拭き取っては逆効果。 まずは水分をしっかり吸い取るためにも乾いた布で吸収させましょう。 大量にこぼした時は、端から拭いてしまうと、押しやられ汚れの範囲が広がってしまうので、フェイスタオルのような長い布で水分を囲みながら吸い取ると拡大させずに済みます。 ●水拭きだけではベタベタしちゃう 汚れを吸い取ったら、水拭きで汚れを落としたくなりますよね。 ウェットティッシュ程度じゃ落とせないかも… と、たっぷりの水で拭いてしまうとフローリングが水分を吸ってたわんだり…傷む原因にもなり兼ねません。 仕方なくウェットティッシュやフローリングシートを何枚も消費して拭いてみるも いつまでたってもベタベタ…べたべた… 足の裏は不快だし、スリッパまでベタベタしてくるし、 「もう!何とかしてー!」 ●糖分を取り除くには「お湯」!? 重曹で拭き取ると良い、とか 中性洗剤を薄めて拭き取ると良い、とか やり方は色々あるようですが、 ここでは 特別な道具も洗剤も使わずシンプルな方法でベタベタを除去したいと思います。 それは 「お湯」です。 もちろん、お湯をかけるのではありませんよ。 熱いお湯をかけた布を固く絞り、ベタベタする床を拭き取ってみましょう。 ジュースなどの糖分はお湯に溶けやすくなりますから、フローリングに残ったままの糖分も、お湯なら緩んで拭き取りやすくなります。 ベタベタが解消するまで、何度か拭き取ってみると良いでしょう。 お湯ならば、二度拭きや洗剤の拭き取りも不要ですから ペットや小さいお子さんのいらっしゃる家庭でも安心ですね。 何より、特別な道具も使わずさっと対処できるので、 粗相しちゃったお子さんにも(時には大人にも) 余裕のあるママでいられます。 あちゃー!こぼしちゃったー!って時に お役立てくださいね。
2016-02-05 09:56:08
引越しの時にとりあえず荷物を詰めてしまった押入れ。
タンスがいっぱいで隣の部屋のクローゼットにまで追いやられた衣類。 「とりあえず詰めた収納」に使いにくさを感じていたら、今から収納をみなおしましょう。 と言っても、すぐに荷物を動かすのではありません。 まずは間取図を用意してくださいね。 間取図が無い方は手書きでOK。部屋と収納位置が分かれば大丈夫です。 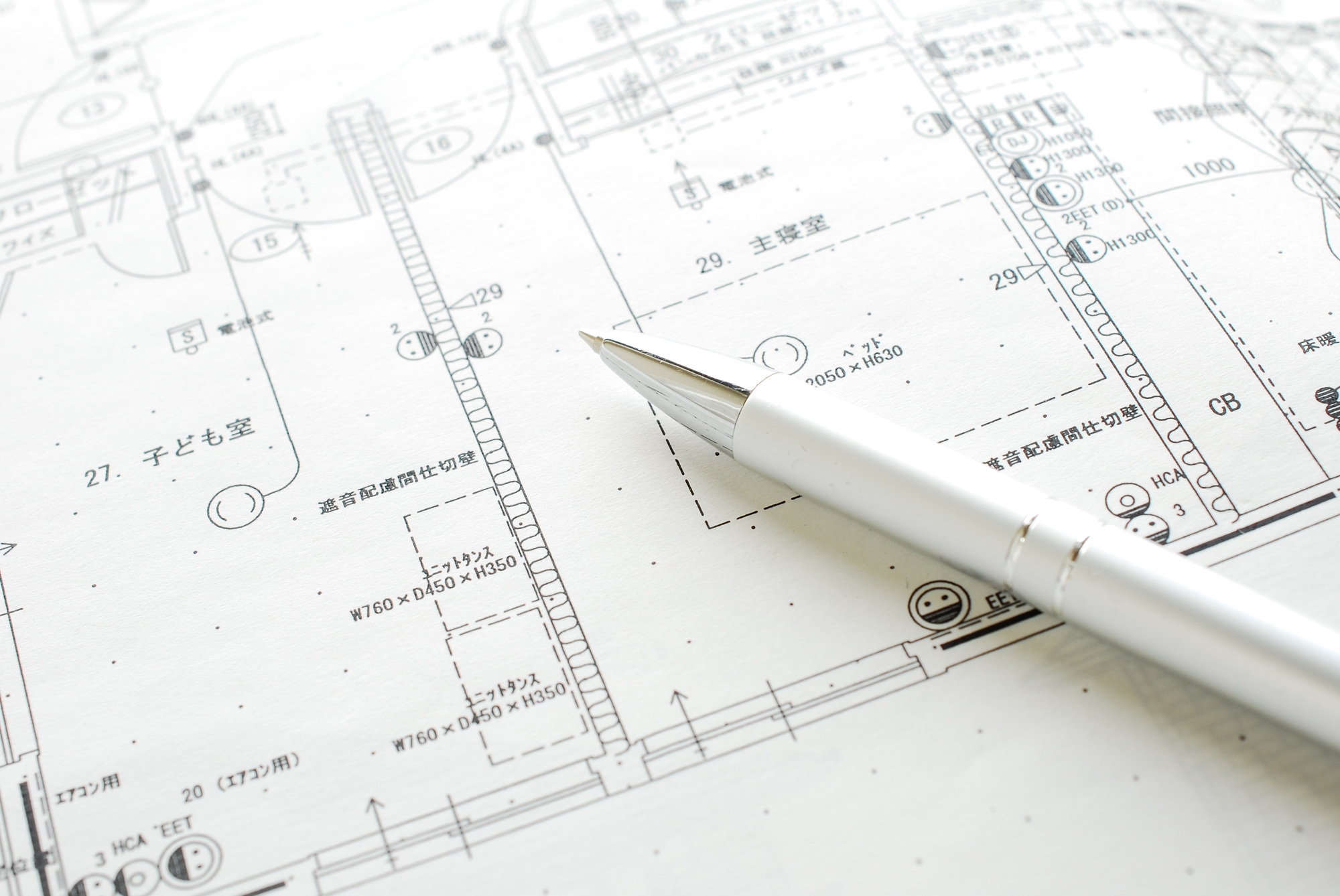 ●手を動かす前に頭で考えると効率アップ いきなり荷物を動かさず、間取図を用意したのは、収納計画を立てるため。 どこに何を入れるのか無計画に詰め込まれた収納は、行方不明が続出のカオス状態になることも。探し物が少なく使いやすい収納にするためには、どこに何を収めるのか収納計画を立てることが大切なのです。 手を動かす前に頭で考えることにより、目的を見失うことなく使いやすい収納に近づきますよ。 ●誰が何をする部屋?誰の何を収める部屋? 間取図を前にしたら、次のように考えます。 1、 部屋の目的を考える 誰が、何をする部屋なの? 例)夫婦の寝室 例)お兄ちゃんの部屋 2、 収納の目的を決める 隣接する収納部には誰の何を収める? 例)夫婦の衣類や寝具 例)お兄ちゃんの勉強道具、学用品 と決めてみます。 すると、 夫婦の寝室にある収納に寝具や夫婦の衣類以外は不要になりますし、 お兄ちゃんの部屋の収納からも勉強道具と学用品以外は移動させる必要がありそうです。 では、 ここで移動対象になったものはどこに収めるのが良いのか? 同じように間取図を使って他の収納部も使い方や目的を考えてみると良いでしょう。 ●誰が、いつ、どこで使うものなのか 部屋の目的だけでは解決しない場合も、 誰が、いつ、どこで使うものなのか考えていくと置き場を決めやすくなります。 例えば ずっとお兄ちゃんの部屋に置きっぱなしだったゴルフシューズと手袋も 「お父さんが」「月1回」「ゴルフで使うシューズと手袋」 ならば ゴルフバックと一緒にトランクルームでもいいかもしれません。 間取図ならば、実際に荷物を移動させることなく、 「ここかな?」「やっぱりこっちの方が便利かな?」 「いやいや、収納の目的と違うから使いにくいな」と置き場を考えたり、手軽にやり直しができて便利です。 ●どこにあれば取り出しやすく戻しやすい? 計画の目途が立ったら荷物を移動してみましょう。 置き場決める時には 「取り出しやすく、戻しやすいこと」が大切です。 また、 間取図ならば生活導線を意識して考えられるので、 「洗濯を干すついでに通る場所はどこかな?」 「学校から戻った時に通る部屋は?」など 家族も使いやすい収納を目指したいですね。 収納を活かすには荷物を動かす前に、間取図で収納計画を立ててからお片付けに取り掛かる方法がおススメですよ。
2016-02-03 10:00:18
春からまた新生活がはじまる子どもたち。
自立のためにも少しずつ自分のことは自分で出来るようになったらなぁと望むママも少なくないのでは? 「ちゃんとしなさい」「早くしなさい」「片付けなさい」と ついつい小言が増えてお互いにイライラすることも。 子どもの「自分でできる」を増やすにはお部屋つくりにヒントがあるようです。  ●自分のモノが把握できる まずは、自分の荷物がどこにあるのか把握できることが大切だとか。 着替えにしても、 「パジャマはどこ?」 「靴下はどこ?」 「昨日もって帰ったバックはどこ?」 と探し物から始まってしまうと、面倒になってしまうことも。 子どもの荷物が置いてあるスペースは、子ども自身が自分の荷物がどこにあるか見て分かるよう一か所にまとめたり、他の家族の荷物と分けるとよいそうです。 例えばクローゼットの中に、お母さんの服と子どもの服が混在していると 子どもたちは自分の服を探すことが困難になることも。 クローゼットを共有する場合は、エリアを区切って視覚的にも お母さんの荷物、子どもさんの荷物。 と分かるようにしておくとよいでしょう。 ●手が届く、目が届く 大人には便利な場所であっても、子どもの身長では難しい場所を選んでしまうと、 子どもの力だけではできないことも。 ・手が届かない高さに制服のハンガーがあったり… ・いちいち背伸びしないと取り出せない引き出しにハンカチがしまってあったり… ・重たいランドセル置き場が高い場所にあったり… 大人でも、手が届かない場所から取り出すことや、 日々使うものが背伸びしないと取り出せない場所にしまってあると ストレスを感じるでしょうし、そのうちに面倒に感じることだってあるはず。 子どもがスムーズに取り掛かるには 行動の妨げになる要因は取り除いて挙げることが得策ですね。 ●モノの置き場が決まっている サッカーに行こうと思ったらボールが無い。 こないだは玄関に置いてあったのに、今日は倉庫にあったし、昨日は子ども部屋だったし。 結局、「おかーさん!!サッカーボールどこ??」と呼び付けることに。 「もう、自分で探して、自分のことでしょ」とお母さんがイライラすることにも。 サッカーボールは「ここ」と共通認識できる場所に置き場があれば、お互いにイライラすることも無くなりそうですね。 「自分でできる仕組み」を取り入れて、お子さんの自立への一歩とサポートしてみませんか?
2016-02-02 09:53:37
新居を選ぶ時の条件にはどんなことが挙げられますか?
間取り、日当たり、駅近、校区、収納、スーパーが近い… 他にはどんな要素がありましたか? これらの候補の中に「周辺の生活道路」は含まれていたでしょうか?  ●意外な落とし穴、生活道路のチェック 部屋から出たら道路を通ってどこかの場所まで向かうことになりますよね。 その道路は自分たちにとって使いやすいのかどうか、お部屋選びの時には忘れがち。 電車通勤の方ですと、沿線の路線は混雑するのか、ターミナル駅なのか、気になりませんか? 生活道路も同じように大切なのです。 例えば、朝は必ず渋滞する道路を使っての車通勤の場合。駐車場からの合流に時間がかかるかもしれませんし、通勤時間は渋滞時間を含めて考える必要があるかも。 ベビーカーで移動することが多い方ですと、歩道の段差や道幅も気になります。 保育園までの道のりはどこを通るのか、歩道橋しかない道、歩道が確保されていない道、ですと気を使いますよね。 帰りが遅くなる方は夜道の安全性も気になるところ。 街灯があるのか、人通りは多いのかチェックしておいた方が安心でしょう。 ●実際に歩いてみる、地図情報サイトも活用しよう 新居を決めるまでに時間のゆとりがあれば、実際に歩いてみることをおススメします。 普段の移動がベビーカーならば、ベビーカ―で最寄り駅やスーパー・公園・保育園まで歩いてみます。 ストレスになりそうな場所があれば回避ルートがあるのかチェックしておくと良いですよね。 通学通勤、帰宅時間に合わせて歩いてみると周囲の様子や混雑状況がイメージしやすいと思われます。 とはいえ 入居先が遠方だとか早々に新居を決めなくてはならない場合は わざわざ現地まで出向くことは難しいですよね。 そんな時にはネット情報を利用してみるのはいかがでしょうか。 渋滞情報サイト、地図サイトでは時間帯別に混雑状況をチェックすることもが可能です。 グーグルストリートビューで実際に利用する道路を歩いてみるやり方もありますよね。 街の様子も伺い知ることができて楽しめます。 ただ、ネット情報が常に最新とは限りませんので参考程度に考えておく方が無難でしょう。 ●街も道路も生活も変化するもの 事前にチェックを完璧にしてみても、入居後の道路の工事で人の流れが変わったり。 近くにショッピングモールがオープンして渋滞箇所が変化したり。 子どもが成長するとベビーカーからも卒業しますよね。 街も道路も生活も常に変化するものです。 何をストレスと感じるのか、どうなったらストレスを感じることなく暮らせるのか、 部屋と同じように周辺環境にも気を配っておくと入居後も快適に暮らせるのではないでしょうか。
2016-01-28 09:59:05
集合住宅にお子様と一緒のお引越しとなったら、
1階物件?2階以上の物件?どちらが良いのでしょうか? セキュリティを考えたら2階以上の物件は、やはり人気が高いようです。 ですが階下への騒音を考えると1階物件にもメリットがありそうですね。 それぞれの特性を見ていきましょう。  ●階段の昇降を考えると2階以上はエレベーターがほしいところ 一人暮らし経験のあるママ(女性)だと、セキュリティ面などから無意識に2階以上の物件を選んでしまう方も。ついつい1階物件は敬遠してしまいがち。 ただ、大人だけで暮らしていた頃と異なり、お子さまとの外出は荷物が多くなります。 ベビーカーに乗せての移動、外出先で寝てしまったお子様を抱きかかえながら重たい荷物をもっての階段の昇り降りというシーンも想像できます。 兄弟、姉妹2人以上になってくると、ますますママの移動も大変に。 やはりエレベーターに対する期待は高まります。 ●住むエリアによってはエレベーター付き物件が希少になることも 2階以上の集合住宅すべてにエレベーターが設置されていれば、希望物件も探しやすいのですが、なかなか難しいのが現状。 4階以下の物件ですとエレベーターが設置されていないことも多く、2階建のコーポやハイツタイプの物件が集まるエリアですと、エレベーター付きの物件を探すことは難しくなってきます。 ●意外に子連れファミリー層に人気の1階物件 ハイツの2階暮らしも選ばれているのですが、あえての1階暮らしを選ばれるファミリーもいらっしゃるようです。 ・階下の騒音を気にしなくていい ・階段の昇り降りが不要なので転落やケガの心配が少ない ・ベビーカーや三輪車に乗せての外出が楽 ・上層階に比べると家賃が安価 など 確かに1階だからこそのメリットとも言えそうですね。 ●セキュリティに安心できれば1階も候補に 1階物件であっても部屋の向きや敷地の広さ、外からの視線を気にせず過ごせる部屋であれば、心配は軽減されるかもしれません。雨戸シャッターが設置されていれば夜も心強いでしょう。 また、単純に1階だから危険、2階以上だから安心とは言い切れず、防犯に関してはどの階であっても注意することには変わりないでしょう。 1階物件が暮らしやすいのか、エレベーター付きで2階以上が安心なのか、 お子様との暮らしで大切にしたいことは何か優先順位を意識しておくことも大切です。
2016-01-26 09:58:10
イ草で織られた畳は、断熱性と保湿性に優れているため、夏に涼しく冬に暖かいのが特徴。
吸水性も高く、乾燥している時には適度な湿気を放出してくれます。日本の風土に適している畳ですが、お手入れが心配で和室つきの物件の選択を悩まれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回は畳を長く使うためのお手入れについてご紹介いたします。  ●畳が苦手なのは、水と湿気と日差し まずは、畳が傷んでしまいやすい誤ったお手入れを知っておくことが、 長持ちさせる正しいお手入れを知るヒントになります。 畳は水が苦手。 変色やカビの原因になる水拭きは避けましょう。 汚れをふき取る時には、揮発性の高いエタノール系の消毒液ですとシミも防げます。 湿気の高い部屋はカビの原因になります。 こまめに換気をして風に当てるよう心がけましょう。 湿度の高い部屋や梅雨の季節には除湿機を利用することでカビ予防に努めると安心です。 布団の敷きっぱなしや、カーペットなどで覆ったままだと通気性が悪くなり、カビやダニの温床になると言われています。 なるべく敷物の無い状態で畳を使いたいものです。 また、直射日光による日焼けは変色を招きます。 傷みも進みますので日差しが強い時は カーテンなどで直射日光を遮ってあげるとよいでしょう。 ●畳の目に沿って掃除機を 普段のお手入れは掃除機で充分ですが 掃除機で強くこすってしまうとイ草が擦り切れることにも。 掃除機ヘッドのブラシはオフにし、畳の目に沿ってかけてあげると良いでしょう。 昔ながらのほうきを使ったお手入れも畳には優しいお手入れ方法です。 ●擦り切れるたら補修テープを利用する方法も 畳の傷みが顕著になるのが、擦り切れ。 細かく千切れてくると衣類にイ草が付着してしまいます。 見た目の美しさも損なってしまいますよね。 天然素材であるイ草は、経年劣化で傷みが出るのはやむないこととも言えますが、 子どもの遊びで畳が強くこすられてしまったり、モノを引きずって擦り切れてしまったら、範囲が広がる前に早めに補修をしておくと良いでしょう。 ホームセンターやインターネットで畳用の補修テープを手に入れることが可能です。 傷の上から貼ることで進行を防ぎ長く使えるよう工夫したいものです。 ●畳の「裏返し」「表替え」で節約を とはいえ、畳は消耗品です。 いつかは取り換える時がやってきます。 ただ、丸ごと新品に買い替える前に、畳表を変えることで節約可能です。 表面のイ草を外し裏返しにする方法が「裏返し」 同じ畳表を使いますので傷みの少ない時期ならば一番節約できる方法です。 次に、表面のイ草そのものを取り換える「表替え」 シミや日焼けなど裏返すだけでは効果が無い場合の手段です。 そして最後が、畳を丸ごと取り換える「新床」になります。 カビの発生や畳の間に隙間が出来きたら取り換え時期になります。 畳を敷いた和室もお手入れ法が分かれば快適に暮らせそうですね。 ほっと寛ぐ畳のお部屋、みなさんの暮らしにもいかがでしょうか。
2016-01-21 09:57:31
お部屋がスッキリ見えない…。
モノは減らしたのにごちゃごちゃした印象を受ける。 片付けだってしているのに。元の場所に収めても何だか雑然としてしまう。 もしかすると 部屋の配色が影響しているのかも?!  ●色が多いとごちゃごちゃするの? お部屋の中は意外といろんな色に溢れています。 ちょっと部屋の中を見渡してみてください。 おもちゃのキャラクターが 赤、青、黒、黄色… 収納ケースは ピンク、緑、白、茶色… テーブルは白で ソファが黒 カーテンが…、カラーボックスが…、 どれくらいの色のグループが存在していましたか? たくさんの色が自己主張することによって ごちゃごちゃ賑やかな部屋を印象づけてしまうことがあるのです。 ●スッキリ見せる部屋の配色は70:25:5 スッキリ見せるには 色の比率を整えてあげることが大切。 配色比率に則って、家具や小物のバランスを調整することで スッキリ見せることも可能になります。 その比率とは 70:25:5 ・基調色 ベーシックカラー 70 ・補助色 アソートカラー 25 ・強調色 アクセントカラー 5 このバランスが乱れると賑やかな印象になるのです。 例えば 白が基調色である部屋に対して 青のカーテンに 茶色のテーブルに 赤色のソファ 黒のカラーボックスに 背表紙がカラフルなマンガがつめこまれていると アクセントカラーにあたるアイテムの比率が高くなり アソートカラーにあたるアイテムが存在しないので ごちゃごちゃ見えてしまうことも。 ●壁、床、天井…面積が広い場所が何色か? ベーシックカラーは 床や壁、天井、扉、など面積が広い場所で考えるとわかりやすいでしょう。 ベーシックカラーに白が多いと明るい印象になり、 茶系が多いとシックで落ち着いた印象になってきます。 ●テーブル、カーペット、ソファ…は何色? ベーシックカラーの次に面積を占める アソートカラー。 家具がアソートカラーになることが多いのですが 床と壁の色が対比している場合は 家具の色によってベーシックカラーに含まれることも。 例えば 濃い茶色の床と、白い壁に、 茶系のテーブルにソファですと 家具と床の茶色の比率が高くなるのでベーシックカラーとなり、 白い壁がアソートカラーの位置付けになってきます。 ●おもちゃが散乱するとアクセントカラーの比率が上がる? 例えば ベーシックカラーが白 アソートカラーが茶色 の部屋で カラフルなおもちゃがあると アクセントカラーに見えることにも。 おもちゃ以外にアクセントカラーのアイテムがあると 比率が上がるため賑やかな印象になってしまいます。 ベーシックカラーや アソートカラーの色に近いアイテムで 上手に目隠ししてあげると バランスよく収まりそうですね。 ●まとめ スッキリ見せるため3色にまとめてお伝えしましたが、 たくさんの色をバランスよく配色された部屋もあるので 色が多いことが一概に悪いわけではありません。 スッキリみせるコツを知った上で 色を活かした部屋づくりを楽しみたいですね。
2016-01-19 09:56:23
自宅を売却して新居に移る時は、
なるべくこちらの希望価格内で承諾してもらいもの。 そのためには購入希望者に「希望価格でも買いたい」と思われることが大事。 値引き交渉しなくてもいいほど好印象を与えられるとが求められます。  ●基本情報以外で差をつける どんな情報が好印象を残す上で大切なのでしょうか? 部屋の間取り? 住環境? ディベロッパー? もちろん、これらも大切です。 ですが、基本情報は仲介業者からも伝えてもらっているでしょう。 あなたが中古物件を選ぶとしたら、 どのような情報をもらえると安心でしょうか? ●住んでいたから分かる魅力を伝えて 例えば 「この部屋は冬には日当たりがよく夏は涼しいので子ども部屋に最適でした」 「キッチンの収納が充実していたのでキッチン家電もスッキリ収まりましたよ」 「近所に未収園児が多いのでお友達つくりも安心でしたよ」 「敷地内の清掃が行き届いているので共有スペースも長持ちしています」 などの情報は実際に暮らしていたから分かること。 この家に住んだら楽しそう、素敵な思い出ができそうだな、 と印象づけられると選んでもらえる1軒になってきます。 ●前向きな売却であることを印象付ける 購入される方が気になるのは 「何か不具合があるから売却するのではないか?」という点。 もし可能ならば ネガティブ情報も上手に伝えると安心材料になります。 「家はとても住み心地が良いのだけれども実家の近くに住み替えたくて」 「転勤で戻る時期が不明なので」 住まいに対する不満ではない、と伝えられれば安心してもらえることでしょう。 正直に伝えることで 「こんな人たちが暮らしていた部屋ならば安心かも」 と思ってもらえると好感度もあがりそうですよね。 ●部屋の第一印象がさらに大事 どんなに住み心地がよいことをアピールされても、 お部屋が乱れ放題では 「本当に大事にしているのかしら?」と懐疑的になりそうです。 清潔感のあるお部屋はモノ言わぬ広告塔です。 まずは部屋を片付けることを始めましょう。 リビングのいらないものを物置部屋に荷物を詰め込む方法だけ解決しません。 なぜならば 物置部屋も収納部も見学されることになるからです。 普段、収納部やキッチン洗面所に人が立ち入る機会が少ないと 抵抗感があるかもしれませんが、 見学を拒否すると悪印象を及ぼしかねません。 一気にモノを減らしたり、 生活感を排除することは難しいかもしれませんが、 掃除をしておく、出しっぱなしを仕舞う、荷物を揃える、など ひと手間かけてあげることが大切です。 時間があれば、新居への引越しも見越して、 片付けのプロに頼るのもひとつの方法かもしれません。 大切に暮らしてきたご自宅が価値を損なうことなく、 次に受け継がれるよう内覧会を効果的に活用したいものですね。
2016-01-14 09:55:50
休日。
お出かけをねだるお子様を前に 「遊園地行く?お金かかるなぁ…」 「電車の移動は周りに気を使うし…」 「ショッピングモールは目が離せないし…」 「やっぱりお金かかるけど遊戯施設が楽なのかな〜」 お子さんとのお出かけにお困りではありませんか?  ●お金をかけるだけがお出かけではない?! ついつい お金をかけた場所で遊ばせないと 子どもとお出かけしたことにならないんじゃないかと 休みのたびにせっせと頑張っているお父さん、お母さん。 遊び方を変えてみると いつもの場所もわくわくする遊び場になりますよ。 それは 大人たちも新たな発見があるかもしれません。 ●行き先は子ども任せで冒険に行こう! いつもは大人が行き先を決め、 移動手段を用意して 連れ出しているかもしれませんが、 今回ばかりはお役御免。 決定権は子どもに委ねましょう。 靴を履いて 家を出るところからスタート。 「さあ、玄関から先は、右ルート?左ルート?」 ●いつもと違う道、いつもは通らない街へ 大人とのお出かけだと目的地ありになるところを、 ぐっと堪えて子どものペースに任せてみましょう。 普段は見過ごしていた場所に路地を発見するかもしれませんね 子どもは隙間が大好き。 路地を抜けると、まるで知らない街のようです。 車で通り過ぎるだけだった隣町も歩いてみると 知らないお店を発見するかもしれませんよ。 「こんなところにパン屋さんがあるんだー」 「ママと一緒にパン買って公園探そうか?」 「あ、ここのスーパー、安いかも!? 今度からお買い物に来よう」 右に曲がる道も 子どもが左に進めば左に。 探検の主役は子どもです。 途中で見つけた小さな公園も 初めての場所だとテンションあがるものです。 「遠くに出掛けなくても眺めがいい場所があったんだね〜」 帰り道も、また探検。 同じルートで復習するも良し、 別の道を迷いながら帰るのも楽しいものです。 ●公共交通手段も加えれば乗りモノに乗る練習に ご近所のお散歩ルートに慣れたら 公共交通手段を利用してみると行動範囲も広がります。 バスに乗って5つ先の停留所で降りてみる。 ちょっと街の雰囲気が変わってくるかもしれません。 お子様に 電車に乗りたいかな?と促してみるのも 行動範囲を広げるきっかけなりますよね。 探検という遊びを通じて 切符を買う、ホームを探してみる、電車やバスに乗る なんて練習も体験できます。 普段、車で移動することが多いお子様にも 貴重な体験になるのではないでしょうか? ●大人の目線では気づかない発見がある 子ども主役の探検。 探検遊びを通じて楽しみながら子どもの主体性を伸し、 大人にとっても、ちょっとした旅行気分が味わえるかもしれません。 いつもの街がまたひとつ楽しくなってきますよ。 |