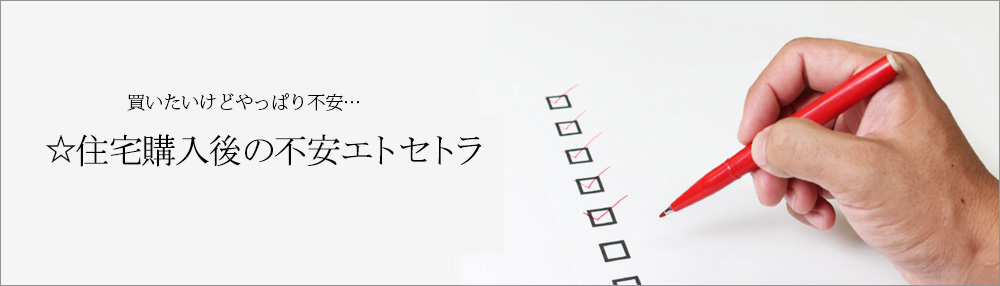
|
<< 2015年5月 >>
記事カテゴリー
月間アーカイブ
|
2015-05-04の記事
次の記事
1/1ページ
2015-05-04 15:46:57
住宅購入は一生のうちでも一、二を争う大きな買い物であることは間違いありませんよね。
住宅ローンを組んで少しずつ返済していくのが一般的ですが、人生一寸先は闇。 失業や事故などで突然支払いが困難になってしまったら…なんて不安もあることでしょう。そんな不安を解消するための対応策をご紹介します。 ●住宅ローンの支払いが困難に陥るケース まずはどのようなときに住宅ローンの支払いが困難になるのかを把握しておきましょう。 代表的な理由としては「教育費」「収入減」が挙げられます。 子供のいる家庭であれば教育費はつきもの。大学卒業までの22年間、学校は公立に通わせるつもりが、子供が私立に行きたいと言い出した…。その他にも塾や習い事など思っていた以上に出費がかさむこともあり得ます。 次に収入減ですが、勤務先の業績悪化によるボーナスカットやリストラはもちろんのこと、夫婦共働きの場合は妊娠・出産などによる収入減や、親の介護のため退職を余儀なくされ見込んでいた収入がなくなってしまうなんてこともあり得る話ですよね。 ●住宅ローンの支払いが困難になったら 住宅ローンの支払いが困難になった場合、まず初めに住まいを「売却」することを考えるかもしれませんが、住宅関連は動くお金が大きいので、うっかりと損をしないためにも、何か困ったら、金融機関や不動産会社、ファイナンシャルプランナーなど、お金や不動産に精通したプロに相談するのが一番ということを覚えておきましょう。 不動産会社に相談した場合、物件によっては売却せずに賃貸に出す提案をしてくれることがあります。周辺に賃貸物件の空室が少ない場合などは、高く貸し出せる可能性があるため、一度安い賃貸や実家に引っ越しをして、マイホームを賃貸に出し、所得が安定したらまた元の住まいに戻ると言ったことも可能です。 金融機関に相談した場合、金融機関にはローンの支払いが困難になった方の相談に乗る義務があるので、相談をする中で支払条件を緩和してくれることがあります。 例えば住宅金融支援機構では「返済期間の延長」「一定期間における返済額の減額」「ボーナス返済分の返済額の変更」など、条件に合わせて返済計画の見直しをしてくれます。 またファイナンシャルプランナーはケースに合わせて返済計画の見直しをお手伝いしてくれるプロです。返済計画の見直しや各種優遇措置、物件の売却や賃貸、住宅ローンの借り換えなど、適切なアドバイスをしてくれるはずです。 ●住宅ローンの支払い困難に陥らないために 支払困難に陥らないためには収支のバランスを事前に把握しておくことが大切になります。インターネットのローンシミュレーションなどによる返済可能額はあくまで一つの目安。そのまま鵜呑みにするのではなく、ご自身の収入・支出がどれくらいなのかをしっかり把握したり、賃貸に住んでいる方なら今の家賃支払いと比較したりして、安心して購入できる金額を自身でも考えてみましょう。 そうは言っても教育費や老後資金など、将来的に必要なお金についてはなかなか想定しづらいかもしれません。そういう場合はあらかじめ学資保険や養老年金などで積み立てておくのも一つの手です。 貯蓄のコツはあらかじめ天引きされた収入の中でやりくりすることです。収入があったら、そこから貯蓄や積立に回すお金を天引きし、残ったお金で生活のやりくりをすればお金が無くなって困るということはなくなります。 天引きするお金は簡単に引き出せないように、定期預金などにしておくのもポイントですね。 せっかく手に入れるマイホーム。不安になり過ぎる必要はないですが、支払困難のトラブルに陥ることなく幸せな生活を送り続けるためにも、しっかりと自身のライフプランと向き合った上で購入しましょう。 ※平成27年5月作成 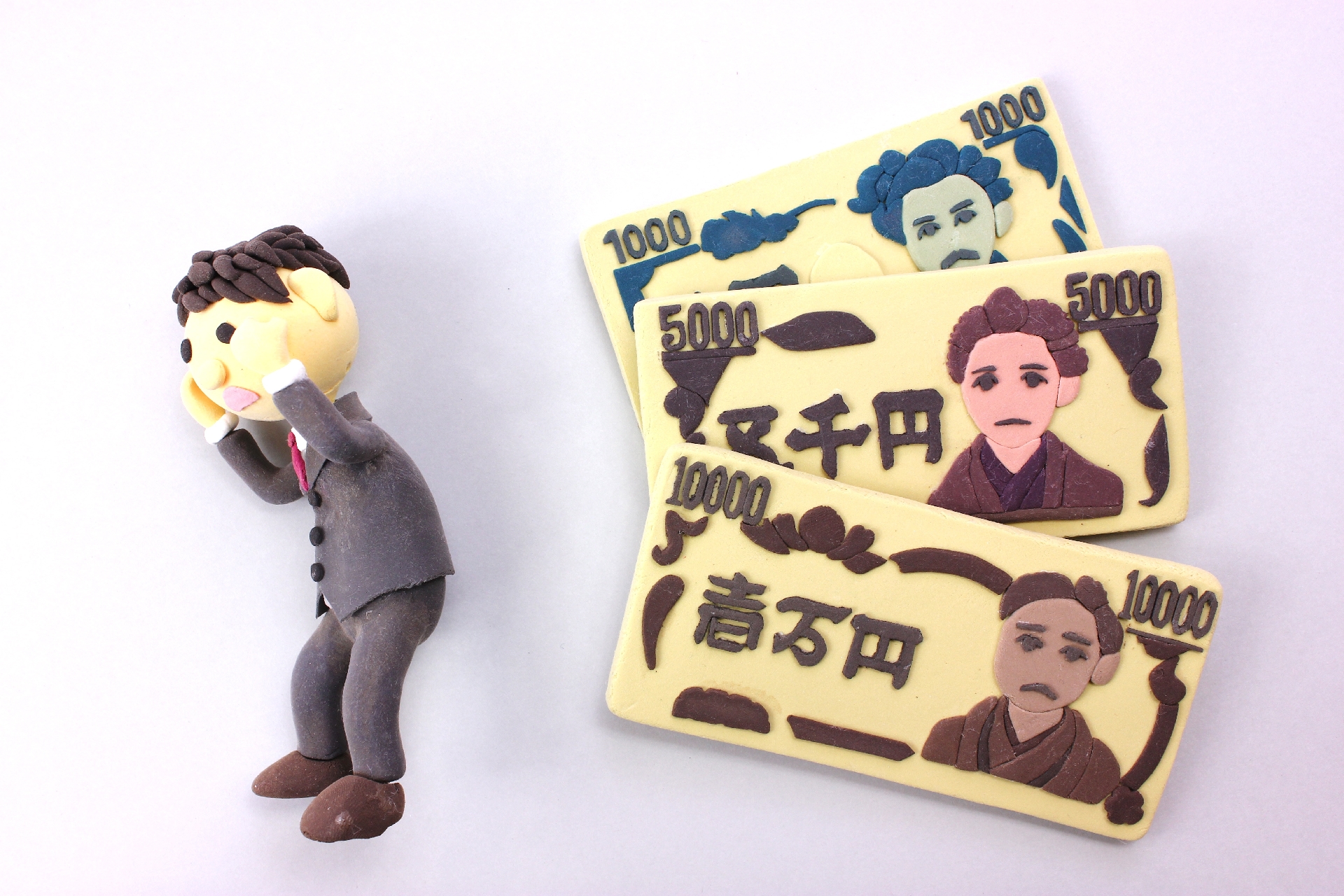
2015-05-04 15:41:52
住宅を購入したらそれで終わり、というわけではなく、各種届出や手続きなどいろいろとやる必要が出てきます。
ここでは、住宅購入後にやっておくことリストと、それを上手に進めていくためのコツをご紹介します。 ●入居前1~3週間前にやっておくことリスト 入居の1~3週間前までにやっておくことは以下の通りです。 ・役所への届出(転出届・転居届) ・国民健康保険の届出 ・電話移転の届出 ・電気、ガス、水道会社への届出 ・新聞、牛乳などの配達店への移転連絡 ・銀行や保険などの住所変更手続き ・クレジットカード会社、証券会社、インターネットプロバイダへの住所変更手続き ・郵便物転送の手続 ・転居ハガキの発送 まずは役所への届出ですが、所定の用紙に必要事項の記入・捺印をして管轄の役所へ提出。そのときに受け取る「転出証明書」が引っ越し後の転入届を提出する際に必要となります。 ちなみに同じ市区町村内での引っ越しであれば「転居届」、それ以外であれば「転出届」となります。 国民健康保険に加入しているのであれば、このタイミングで一緒に届出をしてしまいましょう。 電話の移転、電気・ガス・水道会社への届出は、電話やネットで連絡することができます。移転日を伝えておくことで引っ越し日に料金精算されるので、早めに届出をしておけば安心です。 銀行や保険、各種クレジットカードや証券会社、インターネットプロバイダなど住所を登録しているものについては、早めに連絡・手続きをしておけば直前になって慌てずに済みます。 郵便物転送の手続きはインターネットで手続きをすることができます。インターネット環境がなければ近くの郵便局に運転免許証など本人確認書類を持って行けば手続き可能。1年間無料で郵便物を新居に転送してもらえます。 引っ越ししたことをお世話になった方や親しい友人に伝える転居ハガキ。これは引っ越し直前~入居後が適切なタイミングとなります。 各種印刷会社や写真店などでハガキの作成をインターネット上から依頼することもできるので、自分に合ったハガキを作ってみてはいかがでしょう? ●入居後にやっておくことリスト 入居後~2週間以内までにやっておくことは以下の通りです。 ・電気、水道の使用開始届 ・転入届の提出 ・国民健康保険の手続き ・印鑑登録の手続き ・国民年金の届出 ・運転免許証、自動車登録の変更 ・パスポートの住所変更 入居後すぐに必要となる電気・水道。電気のブレーカーを上げ、水道の元栓を開けてから所定のハガキに使用開始の旨を記入し、数日以内に投函してしまいましょう。 管轄の役所へは転入届の提出、国民健康保険の手続き、国民年金の届出が必要になります。引っ越し後14日以内に届出をする必要がありますので忘れずに。 また印鑑登録は転出届を提出した時点で旧住所から抹消されますので、新住所で再度手続きをする必要があります。役所に行ったついでにやっておきましょう。 運転免許証は新住所管轄の警察署や運転免許試験場で住所変更の手続きをすることができます。住民票の写し、免許証以外の身分証明書類(健康保険証など)が必要となります。 また、県外転居の場合は免許証用の写真が必要になりますので用意しておきましょう。 自動車を持っている人は陸運支局に自動車登録をして、新しいナンバープレートと車検証を発行してもらう必要があります。異なる陸運支局内で住所変更の場合は現車も必要となります。印鑑・車検証・新住民票・車庫証明書も忘れずに。 パスポートは住所や本籍が変わっても同じ都道府県内であれば届出は不要です。それ以外であれば管轄のパスポートセンターに届出をする必要があります。 その他、小中学校に通っている子供がいるのであれば、役所に転入届を提出したタイミングで受け取る「転入学通知書」を学校側に提出する、犬を飼っている人は管轄の保健所に届け出るなどの手続きが必要となります。 ●ヌケモレなく手続きを進めるためのコツ ざっと挙げただけでもたくさんの届出・手続きがあることが分かりますね。 引っ越しや入居のバタバタしているときにこれらの届出を抜け・漏れなくできるか不安になってしまう人も多いのでは…。 そんなときはチェックリストを作ってしまうのがオススメです。各種届出の内容・届出先・期限などを一覧表にしてしまい、いつまでに何をしなくてはいけないかを目に見えるようにしておくだけでもずいぶんと気持ちに余裕が生まれます。 今回紹介した届出以外にも、ちょっとでも気になるものがあればどんどんリストに追加してしまうのがコツ。 やることはたくさんありますが、一つ一つこなしていけば必ず終わりは見えてきます。リストを活用してスッキリとした新生活を迎えましょう。 ※平成27年5月作成 
2015-05-04 15:34:49
せっかく購入した住宅であれば、もちろん大事に長く住みたいものですよね。
そうは言っても買った時点では気づかなかった欠陥が見つかったり、住み続けていく中で設備が壊れてしまったり、火災や地震で建物が損壊するリスクもあります。 少しでもリスクを低減させるためにはどうすればよいか、ケースごとに見てみましょう。 ●買った時点では気付かなかった欠陥が見つかった 住宅の欠陥、例えば雨漏りや白アリによる被害などを「瑕疵(かし)」と言います。特に買主が買った時点では知りえなかった瑕疵を法的には「隠れた瑕疵」と言います。 せっかく買った住宅に欠陥があったら、買主としてはたまりませんよね。このような隠れた瑕疵が判明した場合、買主は売主に対して物件の補修や損害賠償をすることが可能です。 また、欠陥が重すぎて住むこともままならない場合には契約の解除を求めることもできます。このような物件の瑕疵について売主が取るべき責任を法的には「瑕疵担保責任」と言います。 一般的には売買契約の際に「売主が瑕疵担保責任を負うかどうか」「瑕疵担保責任を負う場合は、責任を負う期間はいつまでか」などが取り決められます。 また、契約前に物件のチェックを十分にしておく、売主側への情報提供を求めるなどをして事前に瑕疵を明らかにしておけば、瑕疵担保責任についてトラブルに発展することも少なくなるでしょう。 ●瑕疵担保責任の期間はどれくらい? 売買契約の規定によって変わりますが、物件の売主が不動産会社(宅地建物取引業者)である場合は、中古住宅も含め、2年以上の瑕疵担保責任を負うことが義務付けられています。 なお、新築住宅の場合には、売主である不動産会社(宅地建物取引業者)は、住宅の構造耐力上主要な部分(基礎・柱・屋根・外壁など建築物の荷重を支え、外力に対抗する建築物の基礎的部分)について、10年間は瑕疵担保責任を負う義務があります。 ●個人の方が所有している中古住宅の瑕疵担保責任は? 不動産会社ではなく、個人の方が売主である中古住宅の場合は、売買契約書に「瑕疵担保責任は引き渡しから2ヵ月」といった取り決めがなされていることが多いです。 買主側としては少し短く感じるかもしれませんが、条件をあまりに厳しくしてしまうと売主側としても住宅を売る気にならなくなってしまうので、この辺りが妥決点なのでしょう。 ●住宅設備保証について 長い期間住んでいて壊れてしまうのは住宅だけではありません。システムキッチンやガス給湯器、トイレ・バスなど住宅設備も使っているうちに不具合が発生してきます。 これらの設備が壊れてしまうと、生活していくうえでは困ってしまいますよね。 そこで登場するのが「住宅設備保証」。事前に契約しておくことで、住宅設備の定期的なメンテナンスや故障時の修理・交換をしてくれるサービスです。 必須ではないですが、加入しておくと、いざというときに安心です。 ●火災保険と地震保険のはなし 住宅が壊れる原因は経年によるものとは限りません。火災・風災・雪災・水災・地震など予期せぬ災害で住宅が被害を受ける可能性もあります。 特に地震大国日本では地震による住宅の破損・倒壊や津波による被害は一番気になるところではないでしょうか? これらの被害に対して用意されているのが火災保険や地震保険です。 火災保険は火災による住宅の被害を補償するものですが、他にも風災・雪災・水災・盗難・破損などを補償する総合補償タイプのものが一般的です。 気をつけたいのは高台に住んでいるのに水災補償がついている場合など、不要と思われる補償がついていると保険料は無駄になってしまうこと。 補償のタイプを自由に組み合わせることができる保険もあるようなので、火災保険は自分に必要なタイプのものを選ぶようにしましょう。 また、地震や津波の被害については火災保険では保障されないため、地震保険に加入する人が東日本大震災以降、年々増えているようです。 なお、地震保険は単独で加入することができず、火災保険にセットで加入する形になります。(※どの保険会社でも地震保険の補償内容については同じなので、あまり気にする必要はなさそうです。) せっかく手に入れたマイホーム。今回紹介したケースを参考に長く大事に安心して住むみたいものですよね。 ※平成27年5月作成 
2015-05-04 15:29:56
住宅ローンを組むときに気になるのが金利ですよね。現在は歴史的な低金利が続いており、住宅購入をするメリットが非常に大きいタイミングですが、やはり金利上昇のリスクを考えると少し不安になるものです。
金利について正しく理解し、万が一のときにも慌てないようにしておきましょう。 ●金利の種類と特徴 金利には大きく分けて「固定金利」「変動金利」「当初固定金利」の三種類があります。 「固定金利」はその名の通り、借入時の金利がローンの返済終了まで変わらず、また毎月の返済額も一定となるタイプです。 「変動金利」は半年ごとに金利の見直しが発生しますが、金利変動後も5年間は返済額が変わらないのが一般的です。 「当初固定金利」は「固定金利」と「変動金利」のミックスタイプ。最初の10年間は固定金利、それ以降が変動金利で返済額が計算されるというケースが多いようです。 ●変動金利のルール 固定金利は当初の金利が返済終了まで続き、返済額も一定なので返済計画が立てやすいのですが、気をつけたいのが変動金利。ここでは変動金利の特徴と注意点を見てみましょう。 変動金利は固定金利よりも金利が低いので金利が上昇しない限りは月々の支払額や、総返済額が安く抑えられます。ただし、金利が上昇した場合には返済額がアップします。 変動金利の金利見直しは半年ごとに行われるため、もし仮に金利が急上昇してしまったら、返済額も一気に上昇して返済ができなくなってしまいます!…ということはないのでご安心を。 変動金利の場合、5年間は毎月の返済額が変わらず、見直し後の金利が反映されるのは6年目からというになります。さらに返済額が急上昇しないよう、それまでの返済額の125%が支払額アップの上限とされています。 とはいえ、金利の上昇にしたがって返済すべき総額はアップするため、金利が急上昇してもそれまでの125%しか返済しなければ、利息の返済ばかりで元金の返済がなかなか進まない、…というリスクがあることは覚えておきましょう。 ●金利上昇リスクを最小限に抑えるには 一番確実なのは住宅ローンを固定金利にしてしまうことです。変動金利よりも金利が高く、借入総額や月々の支払額は大きくなるものの、金利上昇のリスクがなく、毎月の返済額がずっと一定なので、返済計画を立てやすいのは一つの安心材料と言えるでしょう。 ただし借りるタイミングには要注意。変動金利よりも固定金利の住宅ローンの方が、先に金利が上がることが多いため、うっかり金利上昇後に借りてしまうと高い金利で返済していく羽目になってしまいます。なるべく金利の低いタイミングを見計らってローンを組むようにしましょう。 また、資金に余裕があるようなら繰り上げ返済を積極的に利用するのも一つの手です。特に変動金利の場合は、金利の低いうちに繰り上げ返済をして元金を減らしておくことで、万が一金利が上昇した際のリスクを低減することができます。 その他にも、多少の費用はかかりますが、より金利の低い住宅ローンへ借り換えをするという選択肢もあります。借り換え前後の金利差が大きい場合に効果的で(※目安は0.15~1%以上)、繰り上げ返済よりも返済額を減らすことができることもあります。 繰り上げ返済と借り換えのどちらがお得かを検討してみるのも良いでしょう。 金利の動向については日本銀行の施策やアメリカの景気など様々な要因が絡んでくるため、長期的な予測は難しいと言われています。この先もしばらくは横ばいとの見通しがありますが、やはり100%確実とはなかなか断言できません。 それぞれのメリット・デメリットを理解し、自身のライフスタイルやライフプランに合わせた住宅ローンを選択するようにしましょう。 住宅ローンの仕組みは非常に複雑です。いろいろ考えてもなかなかスッキリできない場合には、住宅ローンに詳しい不動産会社の担当者や銀行に相談をしてアドバイスをもらってください。自分が気づいていなかった視点で不安を取り除いてくれることもある多いでしょう。 ※平成27年5月作成 
2015-05-04 15:04:48
ようやく手に入れたマイホーム。日当たり良好で眺めも素晴らしい…なんて思いもつかの間、突然家の前に建物が建ってしまった…。そんなことも可能性としてあり得ます。
家の前に建物が建ってしまうことによるデメリットや、それを回避するためのポイントについて考えてみましょう。 ●家の前に建物が建つデメリットって? 家の前に建物が建ってしまった場合、建物の陰に入って日当たりが悪くなる、建物が目隠しになって見晴らしが悪くなる、向こうの建物からこちらの家の様子が見えてしまう…などが一般的な心配事として不安に思う方は多いようです。 また、屋根に太陽光発電用のパネルを設置していたのに、家の前に建物が建ったおかげで日当たりが悪くなり、見込んでいた発電量を達成できなかったなんてことも、可能性としては考えられます。 その他、コンビニなどが建設されたことで、生活が便利になった反面、24時間つきっぱなしの店舗の灯り、治安の悪化が気になることも。 このように家の前に建物が建ってしまうと、生活する上でのデメリットが発生する可能性もあります。 ●不安に思う場合は、住宅を購入する前に土地の用途地域を確認しましょう 家の前に建物が建ってしまい、思いがけないデメリットが発生するのを防ぐためには、住宅を購入する前にその土地についてリサーチをしておく必要があります。 まず、購入する物件の隣が空き地や畑、駐車場など広い土地の場合は要チェック。こういう土地はマンション建設のターゲットになる可能性もあるかもしれません。 そうは言っても、せっかく見つけた物件ですし、必ずしもマンションが建つとは限りません。簡単にあきらめるのもすごく勿体ないですよね。将来の予測をするというのはなかなか難しいですね…。 こんな時、不安を解消するためには、その土地の用途地域を調べてみましょう。土地にはそれぞれ用途地域というものが設定されています。用途地域は大きく住居系・商業系・工業系の3つに分類され、さらにその中で機能的な役割を果たす目的として住居系7つ、商業系2つ、工業系3つに細分化されます。 そして、この用途地域をもとに、「その土地にはどのくらいの大きさの建物を建ててよいのか」が決まっています。「容積率」や「建ぺい率」という建築可能な建物の大きさが決定していくというわけですね。 一般的に工業系の地域は住宅の建築が制限されているため、あまり気にする必要はありませんが、注意したいのは商業系地域。商業系地域は建築の制限が緩く、突然大きなマンションやショッピングセンターが建設される可能性もあります。 なお、これらの用途地域については各行政庁やインターネットで調べることができますし、わからない場合には不動産会社の担当者に聞いてみましょう。自分が家を買おうと思っている場所と、その周辺の土地について事前に調べておけば、思いがけずに大きな建物が建ってしまうというリスクは回避できそうですよね。 ●すでに住居を購入してしまった後なら すでに生活している住居の前に建物が建つ場合は、ある程度あきらめざるを得ないというのが実情のようです。建物が建つということは建築計画に許可が下りているため、少なくとも違法ではありません。したがって法的に解決しようとするのは、あまり良いやり方とは言えません。 ただし日照権の侵害などによって、本来太陽光発電で得るべきだった収益が得られなかった場合は損害として扱うことが可能なケースもあるようです。この場合は弁護士などに相談してみるのも一つの方法かもしれません。 また、大きな建物が建つときは近隣の住民向けに建設会社からの説明会が開催されることもありますので、積極的に参加して疑問や不安をぶつけることも大切なことでしょう。 住宅は購入したら数十年にわたって住み続けるもの。その長い間に家の前に建物が建ってしまうというケースは十分考えられます。そうならないためには、事前に用途地域などのリサーチを行うことは決して無駄ではありません。しっかりと情報集めをすることで将来的な不安を解消してみてはいかがでしょうか? ※平成27年5月作成 
1/1ページ
|